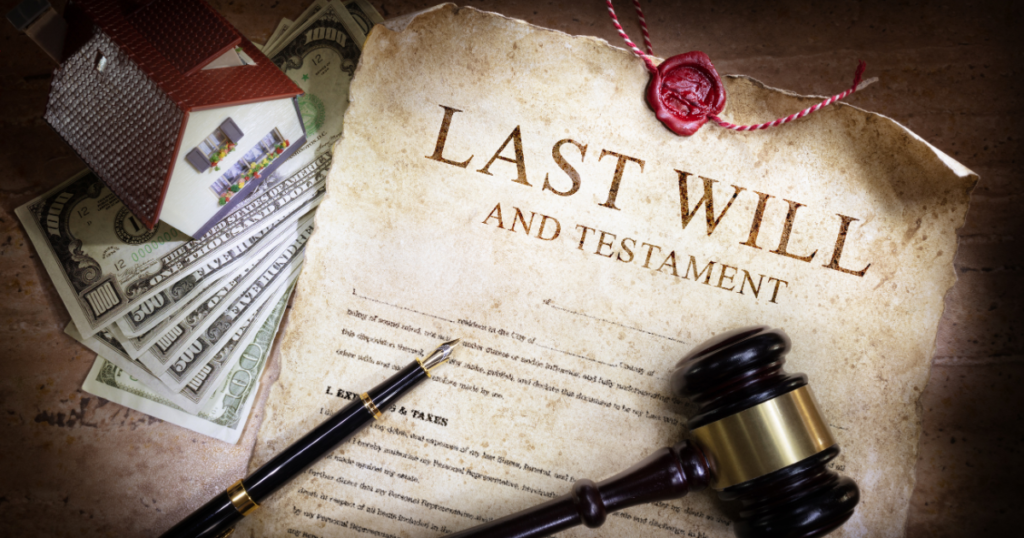遺言書の作成を考えている方へ
相続は、残されるご家族にとって大きな節目となります。
「自分の想いをしっかり伝えたい」「相続をめぐる争いを避けたい」と考える方にとって、遺言書の作成は、円満な相続を実現するための大切な準備です。
行政書士栗田法務事務所では、法的に有効な遺言書の作成をサポートし、ご相談者の意向が正しく反映されるようお手伝いいたします。
遺言書を作成するメリット
✅ 相続トラブルを防ぐ
遺言書がない場合、法定相続分に基づいて分割されますが、ご家族の間で意見が分かれることもあります。遺言書を作成することで、ご自身の意思を明確にし、相続人の負担を軽減できます。
✅ 財産の分配を自由に決められる
法定相続とは異なり、特定の相続人に多く財産を渡すことや、相続人以外の人(内縁の配偶者・孫・友人・団体など)に財産を遺すことが可能になります。
✅ 遺産の管理・活用方法を指定できる
事業を引き継ぐ方を指定したり、相続税対策を考慮した財産分配を行うことができます。
遺言書の種類
遺言書には主に 「公正証書遺言」 と 「自筆証書遺言」 の2種類があります。
✅ 自筆証書遺言
- 遺言者が全文を自筆で書く遺言。
- 2020年の法改正により、財産目録をパソコンで作成できるようになりました。
- 費用がかからず手軽に作成できるが、不備があると無効になる可能性がある。
- 遺言を残したことを誰にも伝えないまま亡くなってしまうと、見つけてもらえないリスクがある。
- 2020年の法改正により、法務局での保管制度(自筆証書遺言保管制度)を利用することで安全に保管可能。
✅ 公正証書遺言(推奨)
- 公証役場で公証人が関与して作成する遺言。
- 遺言の原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクがない。
- 裁判所での検認が不要で、すぐに遺言を執行できる。
- 記載ミスなどによる無効の心配がない。
- 証人2名が必要(当事務所で手配可能)。
公正証書遺言をおすすめする理由
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、書き方に不備があると無効になるリスクが高く、相続人間のトラブルにつながることがあります。また、発見されなかったり、改ざんの恐れもあります。
その点、公正証書遺言は公証人が法的に有効な形式で作成し、公証役場で原本を保管するため、確実に遺言の内容を実現できます。相続人にとって手続きの負担も少なく、スムーズな相続が可能になるため、当事務所では公正証書遺言の作成を推奨しています。
遺言書作成の流れ
- 初回相談(現状の確認・ヒアリング)
遺言書の目的や希望をお伺いし、どのような遺言書が適しているかをご提案します。 - 財産・相続人の調査
戸籍謄本や固定資産評価証明書などを収集し、相続財産の整理を行います。 - 遺言内容の検討・文案作成
ご相談者の意向を基に、法律に則った文案を作成します。 - 公正証書遺言の作成(公証役場手続き)
公正証書遺言を作成する場合、公証人との調整を行い、スムーズな手続きをサポートします。 - 遺言書の保管と見直し
適切な保管方法をご案内し、状況の変化に応じた見直しのご相談にも対応します。
当事務所のサポートの特徴
✅ 法律に基づいた適切な遺言作成
遺言書は、形式の不備があると無効になる場合があります。当事務所では、法的に有効な遺言書を作成するためのサポートを行います。
✅ ワンストップ対応
司法書士・税理士・弁護士などの専門家と連携し、必要に応じて最適なサポートを提供します。
✅ 遺言執行者の指定も可能
遺言の内容を確実に実行するため、遺言執行者の指定についてもアドバイスいたします。
よくあるご質問
Q. どのタイミングで遺言書を作成すべきですか?
A. 遺言書は、早めに作成しておくことをおすすめします。相続人の状況や財産に変化があれば、後から修正することも可能です。「いつか作ろう」と思っているうちに状況が変わることもあるため、思い立ったときに準備を進めるのが理想的です。
Q. 遺言執行者とは何ですか? 指定する必要がありますか?
A. 遺言執行者とは、遺言書の内容を実行する権限を持つ人のことです。不動産の名義変更や銀行の手続き、相続人への財産分配などを行います。遺言執行者を指定することで、相続人の負担を軽減し、遺言の内容を円滑に実行できるため、公正証書遺言とあわせて指定しておくことをおすすめします。
遺言書作成の個別相談を希望する方は、
こちらからお問い合わせください。
相談料:1回 8,800円(概ね1時間前後)