相続の現場では、手続きを進めようとするご家族と、なかなか話し合いに踏み出せない親御さんとの間に、温度差が生まれることがあります。
この「温度差」に悩まれるご家族の姿に、立ち会うことがあります。
たとえば、相続の準備を進めたい長男と、「まだいい」と受け止めようとしない母親。
制度や段取りの話を重ねても、思いはすれ違い、話し合いの場は前に進まない。そんな状況のなかにいると、「なぜ分かってくれないのだろう」という思いが強くなっていきます。
しかし、実際には、そこには「制度」ではなく「心」の問題が横たわっていることが少なくありません。
説得しようとしてもうまくいかないのは、相手が“頑な”だからではなく、その人なりの理由や、言葉にできない思いがあるからです。
今回は、こうした“話し合いに踏み出せない”場面について、考えてみたいと思います。
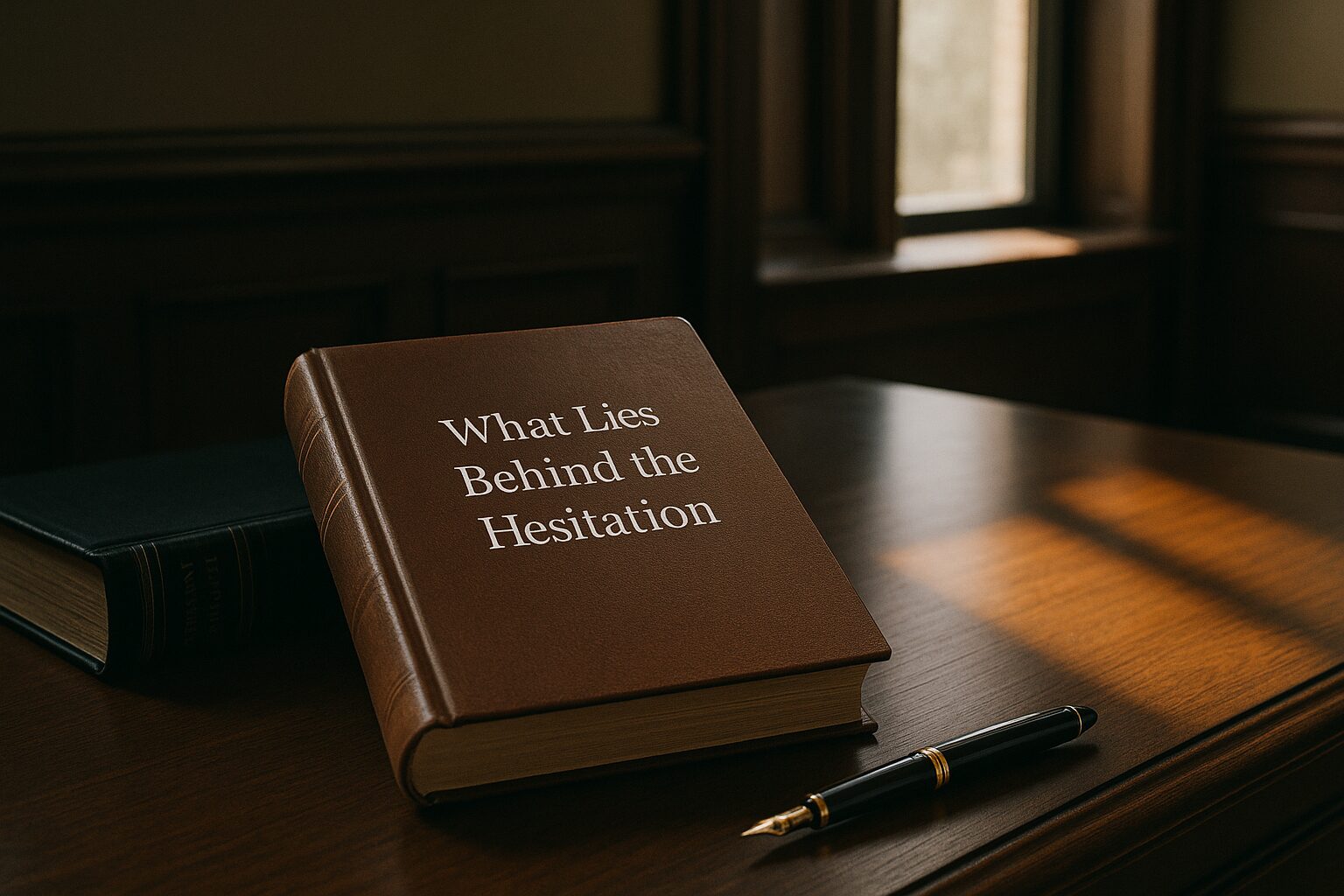
「話す」より「聞く」ことのむずかしさ
相続の話し合いでは、つい“説明する側”と“聞く側”という構図になりがちです。
特にご家族が主導すると、その場がいつの間にか「説得の場」に変わってしまうことがあります。
ご本人にとっては、「知らない世界に踏み込まされるような感覚」なのかもしれません。どれだけ丁寧に説明しても、それが「攻められている言葉」として届いてしまうこともあります。
本当に必要なのは、正しい手順の説明よりも、「なぜ今、話をしたくないのか」「何が不安なのか」を聴く姿勢です。
話し合いではなく、“聴き合い”から始まることが大切だと感じます。
実は、「話す」よりも「聞く」ことのほうが難しい。そんな思いになる場面が少なくありません。
「拒否」は、必ずしも“否定”ではない
相続の準備を「いや」と拒むご本人も、本当は相続そのものを否定しているわけではないことがあります。
「今の生活を変えたくない」
「新しいことに関わるのが怖い」
その思いは、誰にでもある自然な“心の揺れ”です。
“向き合わない”のではなく、“向き合えない”だけなのかもしれません。
表面の言葉に振り回されず、その奥にある気持ちに目を向けること。相続は、制度や書類だけで進むものではないと、感じる場面が多々あります。
第三者の“ほどよい距離”が、扉を開くこともある
家族の言葉は、一番心に届きやすい一方で、一番感情がぶつかりやすい言葉でもあります。
だからこそ、第三者が間に入ることで、空気が少しやわらぐことがあります。
私がご相談を受けるとき、法律の話を一旦脇に置いて、「安心して暮らすための準備」という切り口から話すことがあります。
伝え方や角度を少し変えるだけで、閉ざされていた扉が少しだけ開くことがあるからです。
それは大きな変化ではなくても、家族の対話を前に進めるきっかけになることがあります。
そういう場面に立ち会うときこそ、焦らず、静かに、相手の思いに耳を傾ける姿勢を持ち続けたい。そんな気持ちを、いつも忘れないようにしています。
さいごに
相続や終活の話は、制度や手続きを進める前に「心の温度差」を埋める時間が必要です。
話すことより、聞くことのほうが難しい。
それでも、その難しさに向き合う姿勢が、次の一歩をつくります。
説得ではなく、寄り添うこと。
その小さな姿勢の違いが、会話の流れを少しだけ変えることがあります。そう感じる場面が、少なくありません。

