「公正証書」と聞いて、どんなイメージが浮かぶでしょうか。
公正証書とは、公証人という法律の専門職が、公文書として作成するとても重要な書類です。また、遺言や任意後見契約、死後事務委任など、相続や終活を考えるときにとても大切な役割を果たす書類でもあります。
その公正証書の作成手続が、この秋から大きく変わります。
これまで当たり前だった作成方法に、新しい選択肢が加わることになります。 今回は、10月から始まるこの新制度について、その概要と注意点、実務でどう向き合っていくか、整理してみたいと思います。
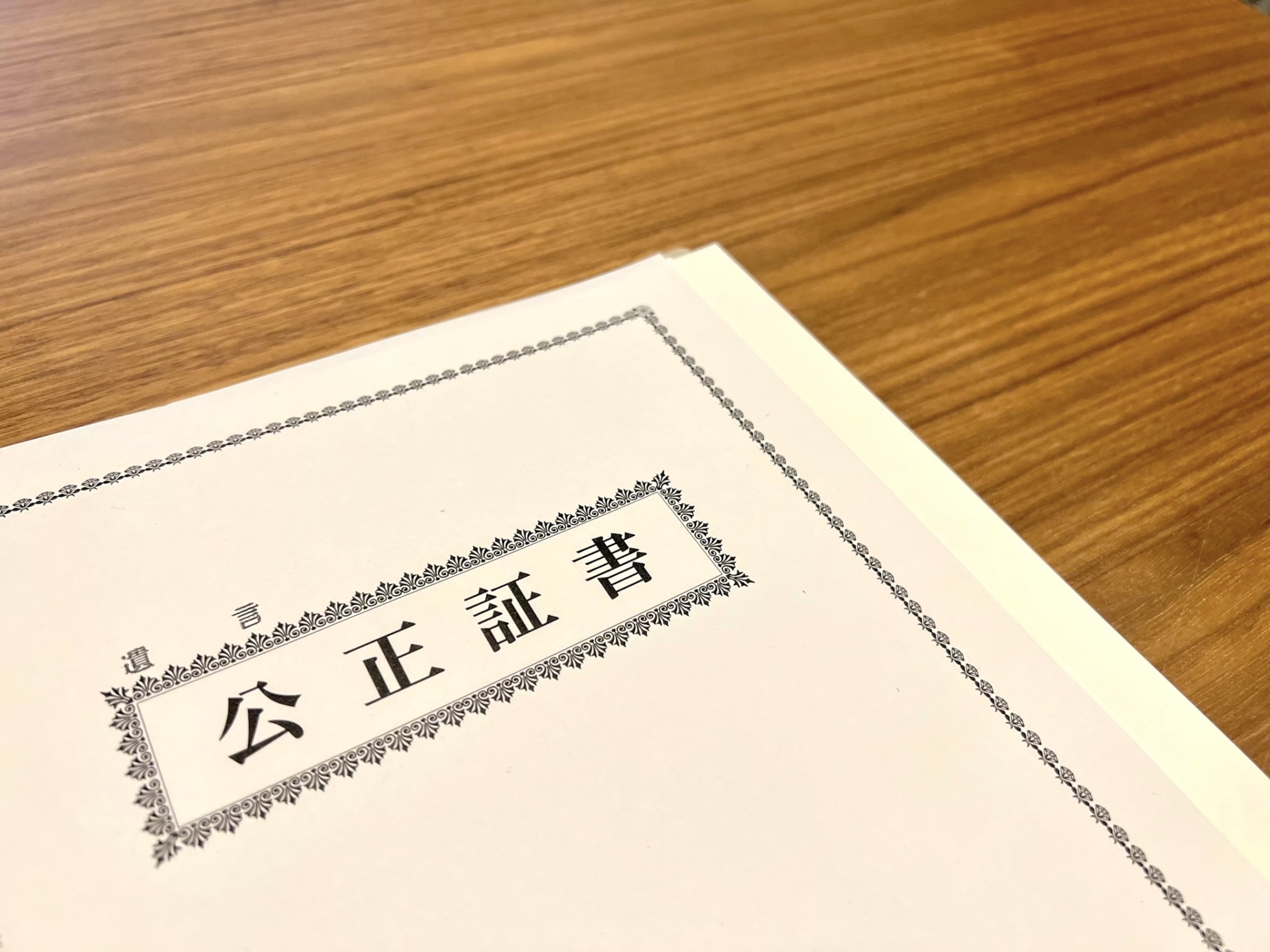
公正証書の手続、これまでは・・・
これまでの公正証書は、原則として依頼者(=嘱託人)が公証役場に出向き、公証人の面前で作成手続きを行うというものでした。
その場で本人確認や内容確認がなされ、合意に至った内容は紙の正本や謄本として作成・交付されます。
公証人の役割は「内容の確認」だけでなく、本人の意思や判断能力の有無を慎重に見極めることにもあります。
だからこそ、実際に顔を合わせ、やり取りすることが基本とされてきました。
また、どうしても来所が難しい方には、従来から公証人が病院や施設へ出張して作成を行う制度もありました。
そして、これからの公正証書は・・・
こうした「紙と対面」が原則だった制度に、今年10月から新たに電子的な作成方式が加わります。この制度は全国一律ではなく、指定された公証人の所属する役場から順次導入されるようです。
今回追加されるのは、次のような方式です
・電子証明書による本人確認
・メールによる嘱託情報の提出(来所不要)
・ウェブ会議(リモート方式)による作成
・公正証書の電子データ化と、電子サインの導入
・紙か電子データかを選べる受取方式
つまり、必要な機器や環境が整っていれば、公証役場に出向かずに、自宅などからオンラインで手続きが完結できるという可能性が出てきたのです。
ただし、リモート方式を利用できるかどうかは、依頼者の希望だけでなく、公証人が「相当である」と判断した場合に限られます。
本人確認や意思確認を適切に行えるかどうかを、慎重に見極めた上で制度の利用が認められるという仕組みです。
新しい方式には、新しい準備も
この制度変更によって、利便性は確実に高まると思います。
ただし、それを活用するには、次のような準備も必要になります。
・電子署名に対応した機器(パソコン、電子ペンなど)
・インターネット接続環境
・タッチ操作可能なディスプレイやペンタブレット
・メールでのやり取りが可能な設定(スマホ・タブレットは非対応)
制度として「できるようになったこと」があっても、すべての方が「すぐに使える」わけではないというのが、実際のところかもしれません。
だからこそ、便利になった分だけ、手続きをサポートする側の役割も大きくなるのだと思います。
さいごに
公正証書のデジタル化は、単に「ウェブ会議で作れるようになった」というだけの話ではなく、これまでの「紙と対面を前提とした制度」が、時代に合わせて少しずつ柔軟になろうとしている、その大きな一歩です。
しかし、どんな制度も「使う人」に合わせてこそ意味があります。
従来の対面方式が安心な方もいれば、新しい方式が必要な方もいます。
大事なのは、制度の選択肢を知り、自分に合った方法を選べるよう備えておくことではないでしょうか。
これから実務の現場でも、少しずつこの制度に触れる機会が増えていくと思います。
そのときに、目の前の方にとって、何が一番良い形なのか。
そんな視点を忘れずに、制度の移り変わりを見ていきたいと思います。

