自由とは自分の思うままに行動できることだと考えがちです。しかし、ドイツの哲学者カントは、自由を「自ら立てた法に従うこと」と定義しました。つまり、本当の自由とは、ただ選択肢があることではなく、「自分で決め、その決定に責任を持つこと」と述べています。
相続や終活において、「まだ先のことだから」と決めずにいると、結果的に法律や家族の判断に委ねることになり、自分の意志が反映されないまま物事が進んでしまうこともあります。
今回は、カントの「意志の自由」をもとに、「自分で決めることの大切さ」について考えてみたいと思います。
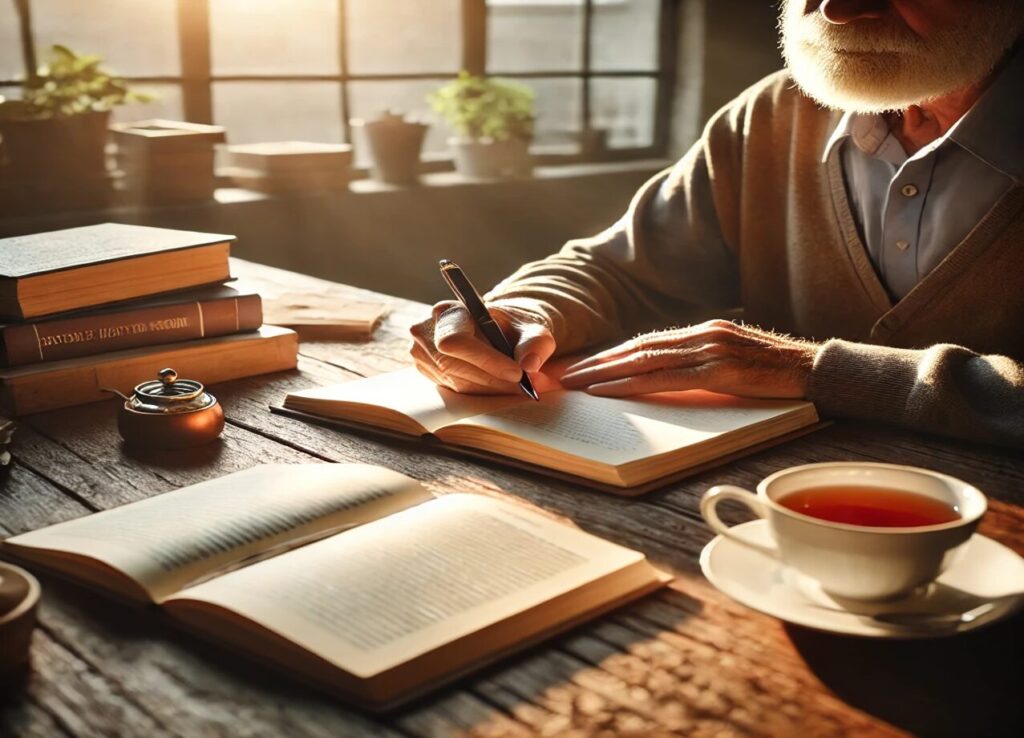
カントの「意志の自由」とは
イマヌエル・カントは、近代哲学に大きな影響を与えたドイツの哲学者です。彼は、人間の理性と道徳を重視し、「自由とは好き勝手に行動することではなく、自ら立てた法に従うこと」と考えました。
カントにとって「意志の自由」とは、単なる選択の幅の広さではなく、理性に基づいて判断し、自らの決定に責任を持つことを意味します。他者の意見や感情に流されるのではなく、自分が考えた「正しい」と思うことを選び、それに従うことが重要だとしました。
また、カントは「道徳法則」についても説き、「人が行うべきことは、個人の利益や欲望ではなく、普遍的に正しいことを基準とすべきだ」と述べています。この考え方は、現在の倫理学にも影響を与えています。
この「意志の自由」という考え方は、相続や終活にも当てはめることができます。人生の大切な選択を、自らの意志で決めていくことは、まさに「意志の自由」を実践することにつながります。
相続や終活における「意志の自由」
相続や終活については、何も決めずにそのままにしておくこともできます。しかし、その場合、いざというときには法律の定めるルールに従うことになり、家族が判断を迫られる場面も出てきます。
たとえば、遺言がなければ、財産の分配は法律の規定に沿って行われるため、自分の希望とは異なる結果になることもあります。また、最期の迎え方や葬儀の形式、供養の方法についても、自分の意思を示さなければ家族の判断に委ねられることになります。
「決めることを後回しにする」という選択には、「気が進まない」という気持ちもあるかもしれません。しかし、何も決めないままでいることが、必ずしも望ましい結果を生むとは限りません。
本当の意味で「自由である」ためには、自分の意志を明確にし、それを形にしておくことが大切です。では、どのようにすれば「自由に決める」ことができるのでしょうか。
「自由に決める」ためにできること
相続や終活について考えるとき、多くの人が「まだ早い」「考えるのが面倒」と感じたり、家族と話し合うことに抵抗を覚えたりするものです。しかし、感情のままに後回しにしてしまうと、自分の意志が反映されないまま物事が進んでしまうこともあります。
まずは、自分が何を大切にしたいのかを整理することが大切です。家族に負担をかけたくないのか、代々受け継がれてきたものを守りたいのか、それとも自分の考えを明確にして伝えたいのか。そうした価値観を見つめ直すことで、選択の方向性が見えてきます。
そして、その思いを形に残すことも重要です。考えているだけでは、自分の意志は伝わりません。エンディングノートに書き記したり、法的に効力のある遺言を作成したりすることで、意思が明確になり、家族も迷わず判断できるようになります。
何をどう決めるかは人それぞれですが、大切なのは、自分の考えを整理し、それを形にすること。そうすることで、カントが説いた「意志の自由」を実践することにつながっていくのではないでしょうか。
さいごに
相続や終活について考えることは、決して簡単なことではありません。どこかで「まだ早い」と思ったり、「家族に迷惑をかけたくない」と考えたりして、決断を先送りにしてしまうこともあります。しかし、何も決めないままでいると、最終的には法律や家族の判断に委ねられ、自分の本当の意志が伝わらないままになってしまいます。
カントが説いた「意志の自由」とは、他人や状況に流されるのではなく、自ら考え、決めること。その考え方は、相続や終活にも通じるものがあります。自分の価値観を整理し、意思を形にすることで、本当の意味での自由を実践することができるのではないでしょうか。
未来のために、今できることを少しずつでも進めてみる。そうした積み重ねが、自分にとっても家族にとっても、より良い選択につながっていくはずです。

