2024年(令和6年)4月1日に「相続登記の義務化」と改正民法が施行され、すでに1年が経ちました。この制度によって、相続手続きは大きく変わりました。今回は制度のポイントをおさらいすると同時に、その背景にある家族の絆や想いについても、あらためて考えてみたいと思います。
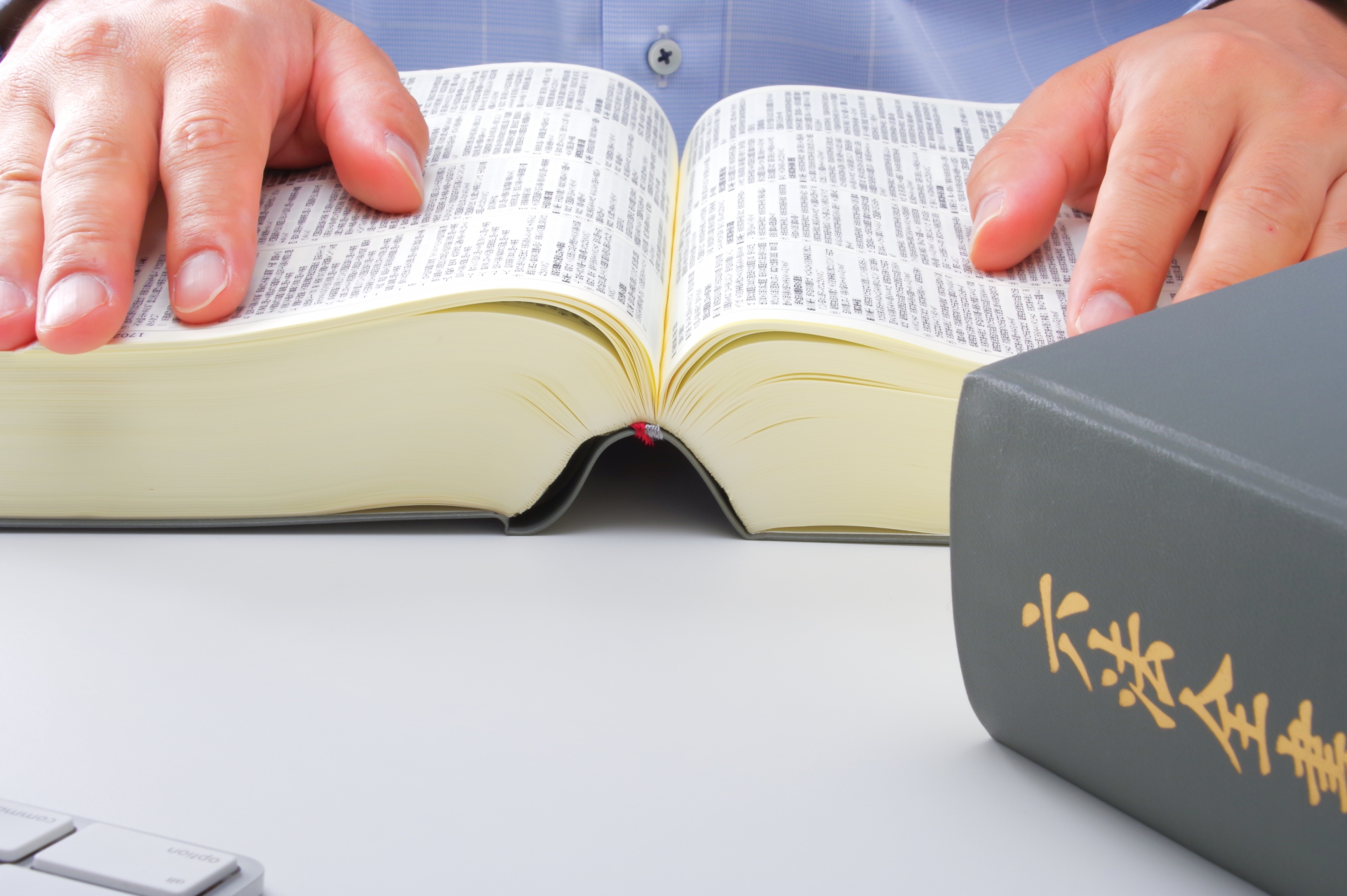
相続登記義務化と改正民法のポイント(手続き編)
相続登記義務化の概要
2024年4月1日以降、不動産を相続した方は、「相続が開始し、自分が不動産を取得したことを知った日から3年以内」に必ず相続登記をしなければならなくなりました。
この義務に違反すると、正当な理由が認められない限り、10万円以下の過料が科される可能性があります。
法定相続人申告登記制度の新設
相続登記がすぐに行えない場合には、一時的に法定相続人の情報を申告することで、登記義務を一旦果たすことが可能です。ただし、これはあくまで一時的な措置であり、最終的には正式な相続登記が必要となります。
改正民法「10年経過後は法定相続分」の規定
改正民法により、相続開始から10年を経過すると、原則として法定相続分での遺産分割となり、『特別受益』や『寄与分』など個別の事情を考慮した遺産分割ができなくなります。
つまり、話し合いを長引かせれば長引かせるほど、家族の想いが遺産分割に反映されにくくなります。
ただし、以下のような例外もあります。
相続開始から10年の期間満了前6か月以内に「遺産分割の請求ができないやむを得ない事由」があった場合、その事由が消滅した時から6か月以内に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求の調停や審判の申立てを行っていれば、10年経過後であっても具体的事情を考慮した遺産分割が認められる可能性があります。
この例外規定を考慮するとしても、やはり相続に関する協議や手続きは早めに行うことが重要です。
実務上の注意点(制度施行後1年の状況)
施行後1年間で以下のようなトラブルが多く報告されています。
・期限ギリギリで慌ててしまい、親族間で揉めるケース
・必要な書類が揃わず、手続きに予想外に時間がかかるケース
以上のようなトラブルを防ぐため、相続が発生したら早めの対応を心掛けたいものです。
改正民法で家族に関わる他の重要ポイント(2024年施行済み)
今回の改正民法(2024年4月1日施行)では、相続登記義務化や遺産分割ルールの見直しのほかに、家族のあり方や親子関係に関する重要な改正も行われています。
・女性再婚禁止期間の廃止
これまで離婚後の女性に課されていた100日の再婚禁止期間が廃止され、離婚後すぐに再婚が可能になりました。
・嫡出推定規定の見直し
離婚後300日以内に生まれた子は、再婚後の夫の子と推定されるなど、実態に即した内容に見直されました。
・嫡出否認制度の見直し
これまで夫のみに限られていた嫡出否認の申立権が子にも認められ、より実態に即した親子関係を築くことが可能になりました。
相続や登記だけでなく、こうした家族に関連する改正も踏まえて、家族全体で制度を理解し、前向きに話し合いを進めていただければと思います。
「家族の想い」に寄り添う相続を(想い編)
制度の本質は「家族の絆を守ること」
私は行政書士として多くの相続案件に携わってきました。その中でいつも感じるのは、相続は単なる財産の移動手続きではなく、「家族同士が心を通わせる機会」だということです。
法律が厳しくなった背景には、不動産の所有者不明問題など社会的な事情があります。しかし、私自身はこれを単なる義務や制約として捉えるのではなく、むしろ家族がきちんと話し合うきっかけにしてほしいと願っています。
相続手続きで直面する家族のリアルな想い
実務の現場では「まだ大丈夫」「いつかやろう」という気持ちが、結果として大きなトラブルに繋がることをよく目にします。
たとえば、「親の想いがよくわからないまま、兄弟間の溝が深まってしまった」「感謝の言葉ではなく、不満が残ってしまった」など、早くから家族同士の想いを確認しておけば避けられたであろうケースが本当に多いのです。
早めの準備が家族の理解を深める
相続手続きを義務化された今だからこそ、制度を「家族の想いを明確にする機会」として使っていただきたいと思っています。
家族で心を開いて「誰が何を引き継ぎたいのか」「親はどんな想いで財産を残すのか」を話し合うことで、手続きは義務から「家族の想いを叶える手段」へと変わります。
「ありがとう」の気持ちでつなぐ相続を目指して
私が目指すのは、家族が笑顔で「ありがとう」と言える相続です。
相続は家族にとって重要な節目です。その節目を「手続きの問題」で終わらせず、家族の想いを受け継ぐ大切な時間として向き合っていただけるよう、専門家として精一杯サポートしたいと考えています。
制度の内容は一見複雑で面倒に感じるかもしれません。しかし、その先にあるのは、「家族の絆」です。
皆様が安心して大切な想いを形にできるよう、いつでもお気軽にご相談いただければ幸いです。
※この記事は2024年4月1日に作成した内容を、最新情報や筆者の想いを反映してリライトしました。

